障がいのある人の参加する演劇について
障がいのある人の表現活動は、少数の天才による場合を除いて、それが行われることへの評価ばかりで、行われた内容に対する評価は留保されることが多かった。単純に言うと、内容には関係なく「よく頑張りました!」という拍手で完結していた。従来のそういう営みを否定するつもりは全くない。一方で、美術の世界で、ハッとするような独特な作品が障がいのある人によって生み出されている。しかし、舞台芸術においては、特に演劇ではまだまだ質を求める実践が多くないというのが現状だと感じる。
障がいのある人が参加する演劇で質を求める場合、二つの方向があるように思う。一つは、障がいに関係なく「普通にやりますよ」というあり方。鳥の劇場と交流の深いニューヨークのTBTB(1979年設立。創立時は視覚障がい者のみによったが、現在は障がい種を限定しない)はこの方向。どんな障がいあっても、それに関係なく、普通に面白い芝居を作って、オフブロードウェーでプロとして高い評価を得ている。車椅子を使っていようと、目や耳に不自由があろうとも、才能のある俳優はたくさんいるわけで、不自由が才能の発露を邪魔しないように、本人や周りが工夫していけばいい。欧米の障がいのある人による演劇実践は、この形が多いように思う。耳が不自由な人による演劇で、セリフは健聴の俳優が吹き替えているものまである。この方向では、障がいのある人をどのように俳優養成のプログラムに乗せるかが課題だろう。
もう一つの方向は、「普通」を目指すことをやめ、不自由を前提としてできることを組み合わせながら、結果として「普通」に対して疑いを投げるような形。我々のじゆう劇場は、そのつもりでやっている。参加者の障がい種は多様で、障がいのない人もいて、年齢も幅広く(中学生から60代まで)、みな素人といえば圧倒的に素人である。が、表現への欲求は強く、エネルギーとチームワークがある。「普通」にはやれないが、「普通」ではできないことがやれる人たち。あくまで素人なのだが、チームとして舞台を作るための「何か」が蓄積されてきているのを、最近感じる。「何か」が何なのかについては現在見極め中だが、ともかく、ちょっと違う素人になってきた。こちらの場合も、状態や能力に合わせた成長のサポートが鍵である。
「スポーツにはオリンピックとパラリンピックの区別がある。しかし、アートにはその区別がないところが素晴らしい」というのは、TBTBの芸術監督ニコラス・ヴィセリさんの言葉。全く同感である。それが人の心を動かすものであるかどうか、それだけが表現の質を決める。だから「障がい者アート」という枠組みや「障がいのある人が作りました」みたいな注釈は、本当はナンセンス。そういうレッテルが消える日が将来来るなら、それが共生社会というものだろう。それまでの過渡的な道具としてなら、「障がい者アート」という言葉もありかもしれない。ともかく見てもらいたい、見てもらわなければ、レッテルが消える日も来ないから。
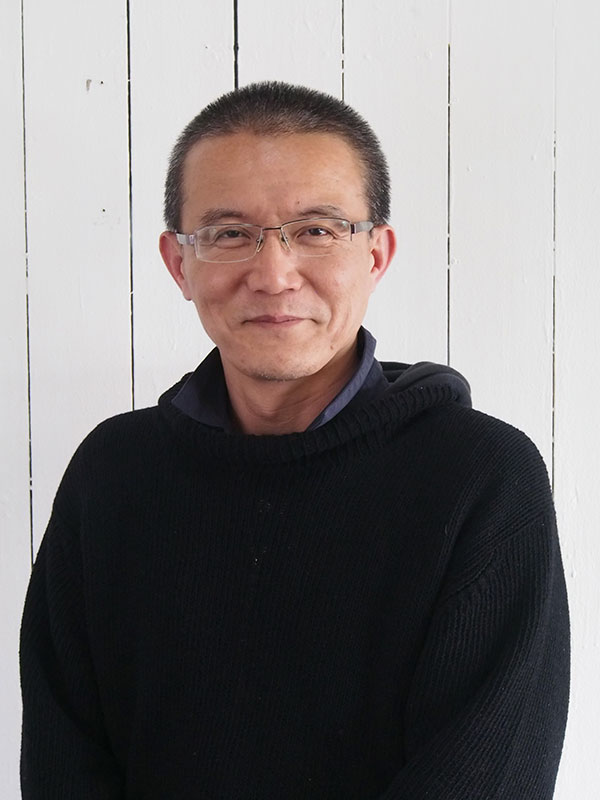
中島諒人
